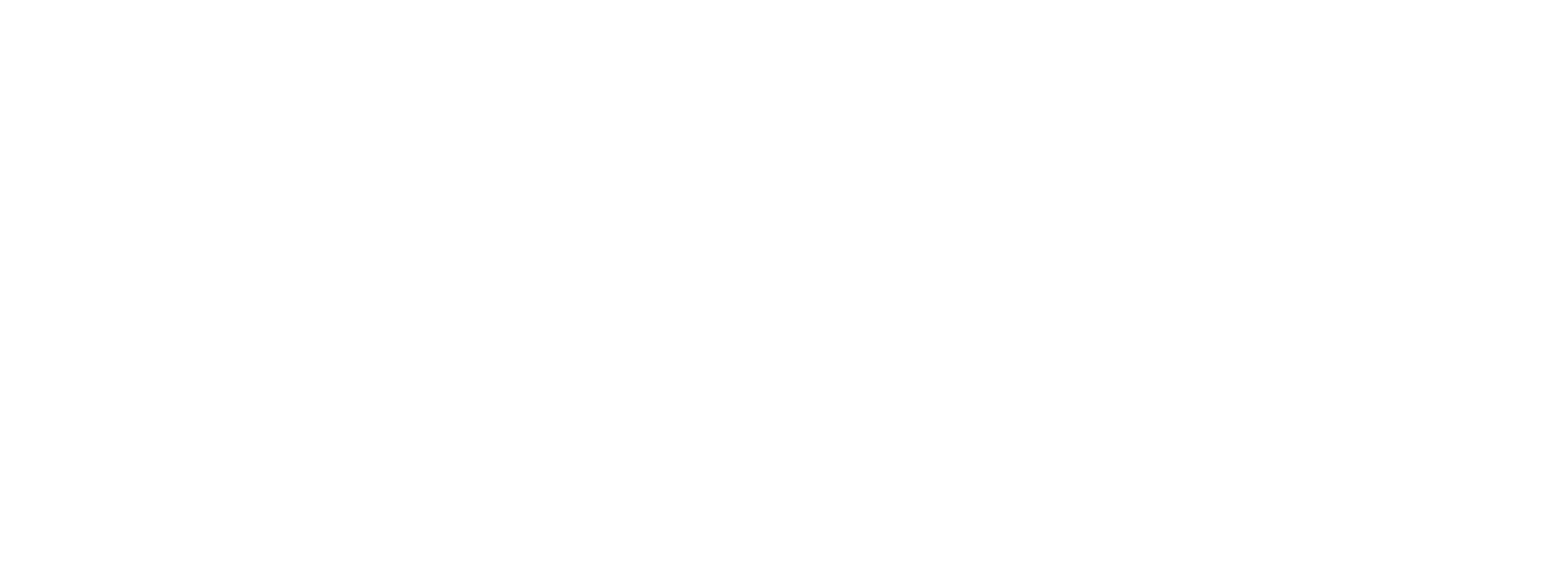アメリカ株投資を始めた皆さん、QYLDやJEPQのような高配当ETFに興味はありませんか?どちらもNASDAQ100の株式をベースにしたカバードコール戦略型ETFであり、10%を超える高配当で大人気です。しかし、私がこの2つを見比べて思ったのは、QYLDの基準価格がずっと下降傾向にある事です。私と同じように、QYLDの株価がなぜ下がり続けるのか、そしてJEPQも同じ道をたどるのか、気になる方も多いはず。この記事では、その理由と展望を初心者向けにわかりやすく解説します。

QYLDの株価下落の原因
QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、NASDAQ 100指数をベースにカバードコール戦略を使い、約10-12%の高配当を実現する超高配当なETFです。しかし、株価(NAV: Net Asset Value)が長期的には下落傾向にあり、その理由は以下の3つです。
1. カバードコール戦略の限界
QYLDは、NASDAQ 100の株を持ちつつ、コールオプションを売ってプレミアム収入を得ます。
逆に、満期日に原資産価格が行使価格を下回った場合は権利を放棄でき、プレミアム分だけを損失として支払いますこれが配当の源ですが、株価が大きく上がると利益が制限され、下落時は損失を抑えきれません。特に、2022年のような緩やかな下落相場では回復が難しく、株価がジリ貧になります。
2. 配当が元本を削る
QYLDの高い配当は、ほぼ元本返還(Return of Capital)で賄われています。「元本返還」は、運用益が不足した場合などに、保有している資産(元本)を取り崩して分配する仕組みです。この場合、投資額自体が少しずつ減っていくため、分配を受けた後の基準価額(資産価値)は下がります。つまり、ETFの資産自体が減り、株価が下がる原因に。長期で見ると、配当を再投資しても成長が少なく、NASDAQ 100(QQQ)に比べてリターンが劣ります。
最初にこれを聞いたときは思わずポンジ・スキームという超有名な詐欺の手法を思い出してしまいました。ポンジ・スキームは新たに加入した人から回収した投資資金で以前に加入した人に配当金を支払い、十分な資金が溜まった時点でいなくなるという、単純ですが現在でもよく使われている最強の詐欺の手法です。ただし、QYLDに関してはそうではなく、正しい運用なのですが、基準価格は下がっていくという構造を持っているという事だそうです。
3. 市場環境と手数料
QYLDはテック株中心のNASDAQ 100に依存し、ボラティリティが低いとオプションプレミアムが減少し、収入が落ちます。さらに、0.60%の手数料が長期で負担になります。投資家からは「短期収入向けだが長期は厳しい」との声もあるようです。
JEPQも同じ運命?将来性を考える
JEPQ(JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF)もカバードコール戦略を採用し、約9-12%の配当を目指しますが、QYLDより遅く販売開始されている分、改善点があります。QYLDが2013年に設立されたのに対し、JEPQの設立は2021年です。JEPQが将来QYLDのようになるかを考えてみましょう。
QYLDとJEPQの違い
- オプションの柔軟性:QYLDは100%カバー(全株にオプション)ですが、JEPQは20-80%で調整可能。これで上昇相場でも利益を一部確保することができます。
- 手数料:JEPQは0.35%とQYLDの0.60%と比べると低めです。
- パフォーマンス:過去3年でJEPQは約64%、QYLDは約36%の総リターン。JEPQの方が有利。
JEPQの2025年以降の展望
- 良い点:柔軟な戦略でQYLDより下落リスクが低い。2025年は米国の債務問題や税制変更でボラティリティが上がれば、プレミアム収入が増え、配当が魅力的になる可能性。AI・テック株の成長も一部取り込めます。
- 課題:下落相場では保護が限定的で、株価下落リスクは残る。長期成長を求めるなら、QQQのような純粋なインデックスETFが有利。
投資のポイント
- QYLD:短期の収入狙いなら検討可だが、長期では株の基準価格下落で資産が目減りする可能性も。配当金に対する税金(普通所得扱い)にも注意が必要。
- JEPQ:QYLDよりマシだが、強気相場ではインデックスよりは成績は劣ります。2025年はボラティリティ次第で魅力的だが、リスク分散が必要。
- おすすめ:長期投資ならS&P500、オルカン、NASDAQなどで成長を優先。配当重視ならJEPQを少額で試し、市場動向を注視するのがより安全。
JEPQはまだ基準価格が下がる可能性は少ないと考えられますが、まだ歴史が浅いので今後も動向は注意してみておく必要があります。
まとめ
QYLDはカバードコールの仕組み上、株価下落が避けられず、長期投資には不向きです。JEPQは改善されていますが、同じリスクを完全には回避できません。投資は目的に合わせて選び、分散を忘れずに!
私は今後もJEPQへの投資をしばらく続けていきます。気になる配当金は毎月レポートしていこうと思います。
※投資は最終的に自己判断、自己責任の世界です。この記事にはあくまで私の実体験とその感想を書かせていただきました。誰がなんと言おうと最後は自分の判断で投資を行って下さいね。
今日はJEPQから分配金$469.83(約7万円)頂きました。自動再投資され、更に8.5株ほど増えました。しばらくはJEPQに注力して分配金を増やして行こうと思います。10倍持てば月70万円か。夢あるね。 https://t.co/CeM1LE0Bp4 pic.twitter.com/QKJIYmNgqX
— おりべ@アメリカで株始めました。 (@oribe_usa) September 5, 2025